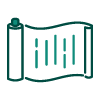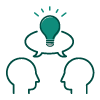本日は、
山口県福祉サービス運営適正化委員会の研修会において
カスターマーハラスメントへの理解をテーマに
弊所/石﨑がお話する機会を頂戴しました。
今回は、
県内の高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉事業所のみなさま
計239名の参加お申し込みを頂き、
当日の天候等の影響を受けキャンセルもあったものの
220名を超える方にご参加いただきました。
お忙しいところ、貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございます。
弊所/石崎が施設内研修にお伺いする機会は、
高齢者福祉事業のお客様が多いため、
障がい者福祉や児童福祉事業からの参加者のみなさまの
現場の実態とピントがズレていたのではないかと心配しておりますが、
お役に立てることが一つでもございましたら幸いです。
行政機関や民間大手企業を中心に
ここ1年くらいで急速に
カスタマーハラスメントに対するポスターや方針を
店舗や事業所で目にすることも増えてきました。
一方で、
ご利用者・ご家族を支える役割を担われている福祉事業所では
その性質上、割り切った対応がはばかられるという認識もあって
事案発生時の対応やその予防的な取り組みに
戸惑いが見られるのも事実です。
今回の研修では、
世の中の変化をご紹介しつつ、
・ 講師の体験談
・ 介護現場の暴力・ハラスメントの定義
・ 対応困難者はどんな人なのか
・ 個人の技量に頼らず組織で行う準備・対応
などについて、お話させて頂きました。
ハラスメント全般に、
事案発生後の「後捌き」の部分に目を奪われがちですが、
事案発生が起こらないようにするための「前捌き」が大切だと考えます。
この「前捌き」には、
事案が発生しても加害者を生まない対応も含まれ、
そこでは、対応マニュアル等の作成とや現場の理解等が重要になると思われます。
理不尽なクレーム等を上手にさばく人に頼るのではなく、
各事業所において、
組織で共通理解を育み、事案発生時には協力して対応できる備えを
弊所としてもご支援していければうれしいです。